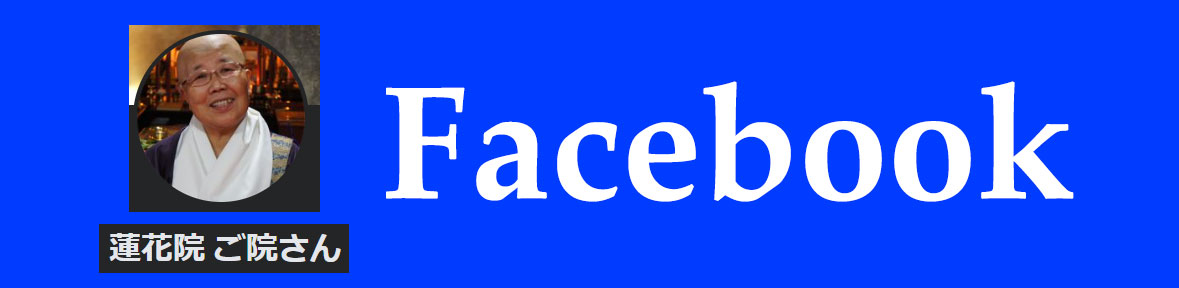あなたはしあわせですか?
何をやってもうまくいかない。努力が報われない。
家庭環境や人間関係の不協和音。精神的な圧迫、マイナス思考。 自分自身の身体問題、そして自分を中心とした世界が少しづつ傾斜していく不安
ある時、突然それは始まります。
小さなしこりがだるまのように膨らんでいく。心に闇が蔓延する前に、悪いことが起こる前に、その不安の原因を知ることが大切です。
家庭環境や人間関係の不協和音。精神的な圧迫、マイナス思考。 自分自身の身体問題、そして自分を中心とした世界が少しづつ傾斜していく不安
ある時、突然それは始まります。
小さなしこりがだるまのように膨らんでいく。心に闇が蔓延する前に、悪いことが起こる前に、その不安の原因を知ることが大切です。

運命・因縁透視
あなたの運命や運勢、因縁を透視します。不幸の種が見つかるかもしれません。誰にでも因縁はあるのです。あなたが先祖から受け継いだ幸せの種や不幸の種を見つけるのです。そして不幸の種を幸せの種へと変えるのが大切です。
姓名判断、事業繁栄、恋愛、縁談、子宝(不妊)、受験、就職、病気、行方不明の人探しなどさまざまなことでお悩みの方。ご相談される方の生年月日をお聞きし、霊感・霊視によって、蓮花院住職が解決の指針を鑑定いたします。
姓名判断、事業繁栄、恋愛、縁談、子宝(不妊)、受験、就職、病気、行方不明の人探しなどさまざまなことでお悩みの方。ご相談される方の生年月日をお聞きし、霊感・霊視によって、蓮花院住職が解決の指針を鑑定いたします。


身体の弱った方には、遠隔祈祷をする場合もあります。
ご相談に見える方は、病気でお悩みの方、精神的に不安定になっている方、行方不明の人探し、子宝(不妊)を授かりたい方が多いようです。
透視というとなにか固い感じがしますが、単なる占いではなく、どうすれば解決できるのかというというところまで、見通すことだとご理解いただければ幸いです。
御法山・蓮花院では、現在お悩みのあなたの運命、運勢を鑑定し、より幸福な、未来に開かれた人生を送っていただけるように開運のお手伝いをすることだと思っております。
蓮花院では人生相談を承っています
人には不思議なアンテナがあります。それは皆、平等に持っているものです。
そのアンテナが感じたことは、錯覚でも思い過ごしでもありません。
生きてきた状況、環境、人間関係、あらゆる世界に理由があるのです。
まずはその原因の種を知ることだと思います。
蓮花院ではご相談を承っております。どんなことでも大丈夫です。
幸せになることをためらってないで、ほんの少しの勇気を出してください。まずご連絡して下さいね。
そのアンテナが感じたことは、錯覚でも思い過ごしでもありません。
生きてきた状況、環境、人間関係、あらゆる世界に理由があるのです。
まずはその原因の種を知ることだと思います。
蓮花院ではご相談を承っております。どんなことでも大丈夫です。
幸せになることをためらってないで、ほんの少しの勇気を出してください。まずご連絡して下さいね。
ご家族のご相談
ご本人がいらっしゃらない場合、ご家族のみのご相談をお受けしております。
過去のトラウマ(心の傷)、うつ、依存症、家庭内暴力、少年少女非行、いじめ、親子のコミュニケーションの問題、職場における人間関係、恋愛など・・・
こんな状況から何とか抜け出したい、病院や公共の相談所にも行ったがなかなか良くならない、自宅での毎日で家族も疲れ果ててしまっている。本人を刺激しない様に家族で見守っているものの全然状況が変わっていかない。
こんな状況から何とか抜け出したい、病院や公共の相談所にも行ったがなかなか良くならない、自宅での毎日で家族も疲れ果ててしまっている。本人を刺激しない様に家族で見守っているものの全然状況が変わっていかない。

蓮花院では、ご家族のみのご相談も承っています。ご本人がいらっしゃらなくても大丈夫です。どんなことでもご相談くださいね。
家相
家庭内に問題が起りがちだったり、病人が出たりする時は、家相や方位から来る原因も考えなければなりません。どうぞご相談くださいね。
方位・方角
新築、増改築、移転などの諸工事する場合は、家相・方位を確かめ、方罪にあたる場合「方罪除け祈祷」を受けることが肝要です。引越しや家を建てる場合は必ず、土地と図面の確認が必要になります。
鬼門除け
家の中の北東、または北北東に貼ってください。家屋には必ず『鬼門』があり、そこから邪気が入ると言われています。家族の健康を害することがあるので気をつけなければなりません。家の中で特に大事な個所が、玄関・台所・便所・鬼門です。このお札で、邪気を払い清め、快適に生活しましょう。どんなことでもご相談ください。

家祈祷(やぎとう)
家払いとも言い、家屋・地所に感謝の法味をささげたり、障っている諸々の因縁を払う祈祷です。
土地の上に建物を建てることを前提としてその土地の守護神、地神、様に家内安全を祈願いたします。種々の因縁等が関わっていたりまた、その土地の邪気を払い、土地を供養し、因縁関係の諸霊を成仏させるのです。さらに工事が障りなく順調に完成するように祈願することをいい、因縁退散と吉祥清浄の修法祈祷によって、祈念するのです。蓮花院では家祈祷を行っています。どんなことでもご相談ください。

土公供(どこうく)
これは大地をつかさどる護法神である地天(じてん:堅牢地神とも)を供養する儀式で、大地は地天の所領であるため、土地をもらうために行います。
土を司る土公神(どこうしん 「地神」ともいいます)を供養するために祭壇の前に盛り土をしてその中に米・樒・香・五穀・水等を注ぎ、読経を行います。蓮花院では土公供を行っています。どんなことでもご相談くださいね。
土を司る土公神(どこうしん 「地神」ともいいます)を供養するために祭壇の前に盛り土をしてその中に米・樒・香・五穀・水等を注ぎ、読経を行います。蓮花院では土公供を行っています。どんなことでもご相談くださいね。
法事・回忌法要
初7日忌~5・7日忌(35日)、7・7日忌(49日)、100ヶ日忌、1周忌、第3回忌、7回忌、13回忌、23回忌、50回忌・・・と年回忌ごとに追善供養します。お亡くなりになってからはご遺族中心に7日ごとにご供養していきます。尽7日の49日には霊位が彼岸に往詣しますので、49日忌法要後納骨供養いたします。生きていても亡くなられても魂の縁は続いていくのです。

初七日
告別式当日に式中または戻り初七日という形で行うことが多いです。初七日、二七日、三七日、四七日、五七日、六七日、七七日となります。七七日
49日です。本位牌をご用意いただけましたら、お葬儀以降使用した白木お位牌はお焚き上げ頂きましょう。(この場合、七七日忌法要、位牌開眼法要の二法事となります)百カ日
新規にお墓を建立した場合、この日に納骨という方が多いようです。(この場合、百カ日忌法要、石塔開眼法要、埋葬法要の三法事となります)一周忌
1年目の法要です。三回忌
2年目の法要です。3年目と間違える方がいらっしゃいます。ご注意下さい。 以後、七回忌、十三回忌、三十三回忌と行う方が多いです。本来十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二十七回忌、三十三回忌、三十七回忌、四十三回忌、四十七回忌、五十回忌、百回忌と続きます。法要について
お導きの仏さとして十三仏(不動、釈迦、文殊、普賢、地蔵、弥勒、薬師、観音、勢至、阿弥陀、阿閦、大日、虚空蔵の仏さま)が配当され、精霊は施主の勤めるご法事を縁として十三仏を順次巡り、それぞれの仏・菩薩の徳を授かり、子孫に福徳を施してくださると信じられてきました。そこで、今日でも特に功徳があるとされる年回(1年、3年、7年、13年、33年など)の故人の命日に、年回忌法要を行い故人の冥福や菩提のために法要を営むことが大切とされています。

年回忌法要では、亡き人の遺族が施主となって、仏さまに焼香・花・飯食(供物)・燈明・卒塔婆などを供養し、導師(僧侶)が、その善行の功徳が故人(精霊)の冥福や菩提のためになるように読経や修法を行います。亡くなった後に、追って福徳を施し故人に代わって善行を修するための供養なので「追善供養」といい、功徳を故人の冥福や菩提のために廻らし向けるので「追善廻向(ついぜんえこう)」ともいいます。
蓮花院では回忌法要を行っています。お電話、メールでご相談を承っています。どんなことでもご相談してください。